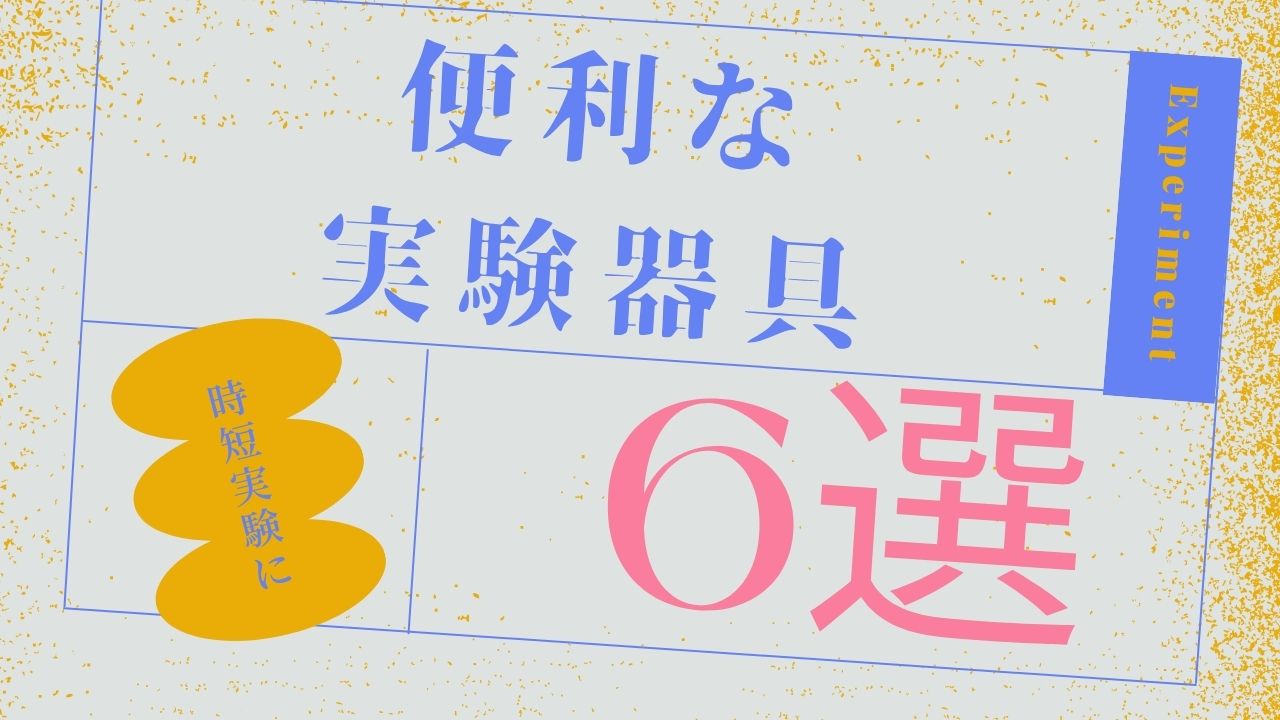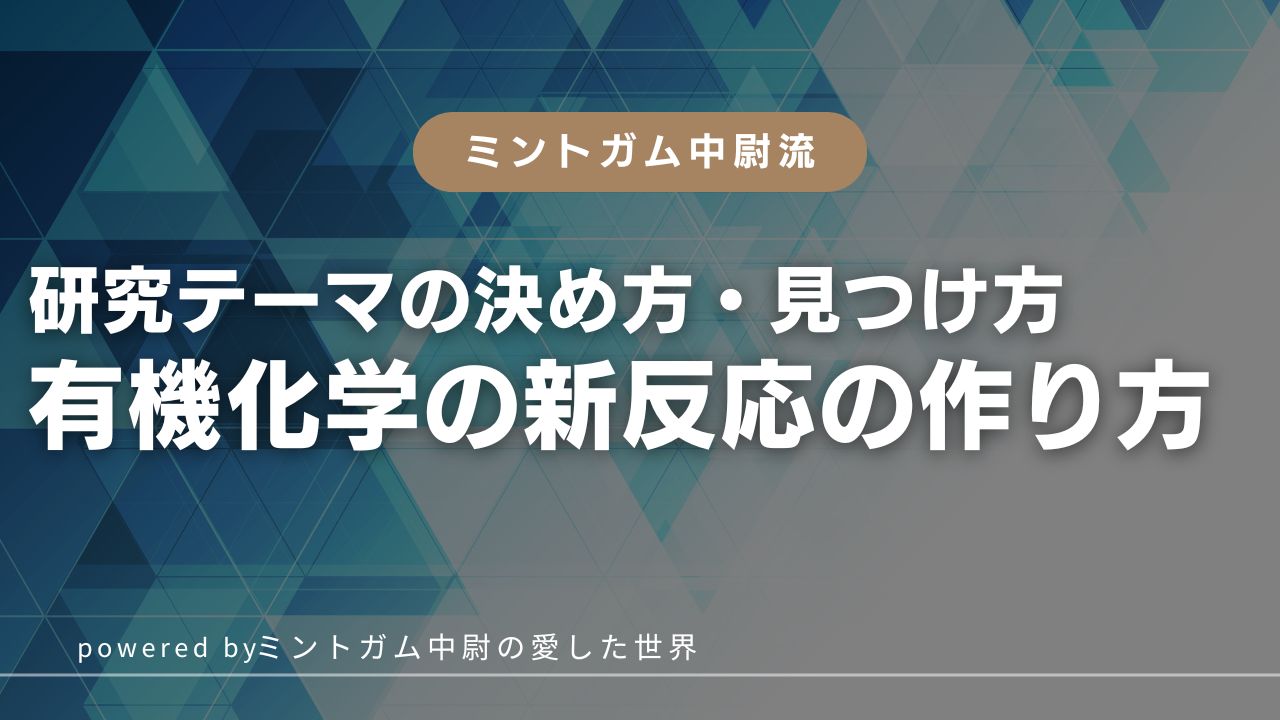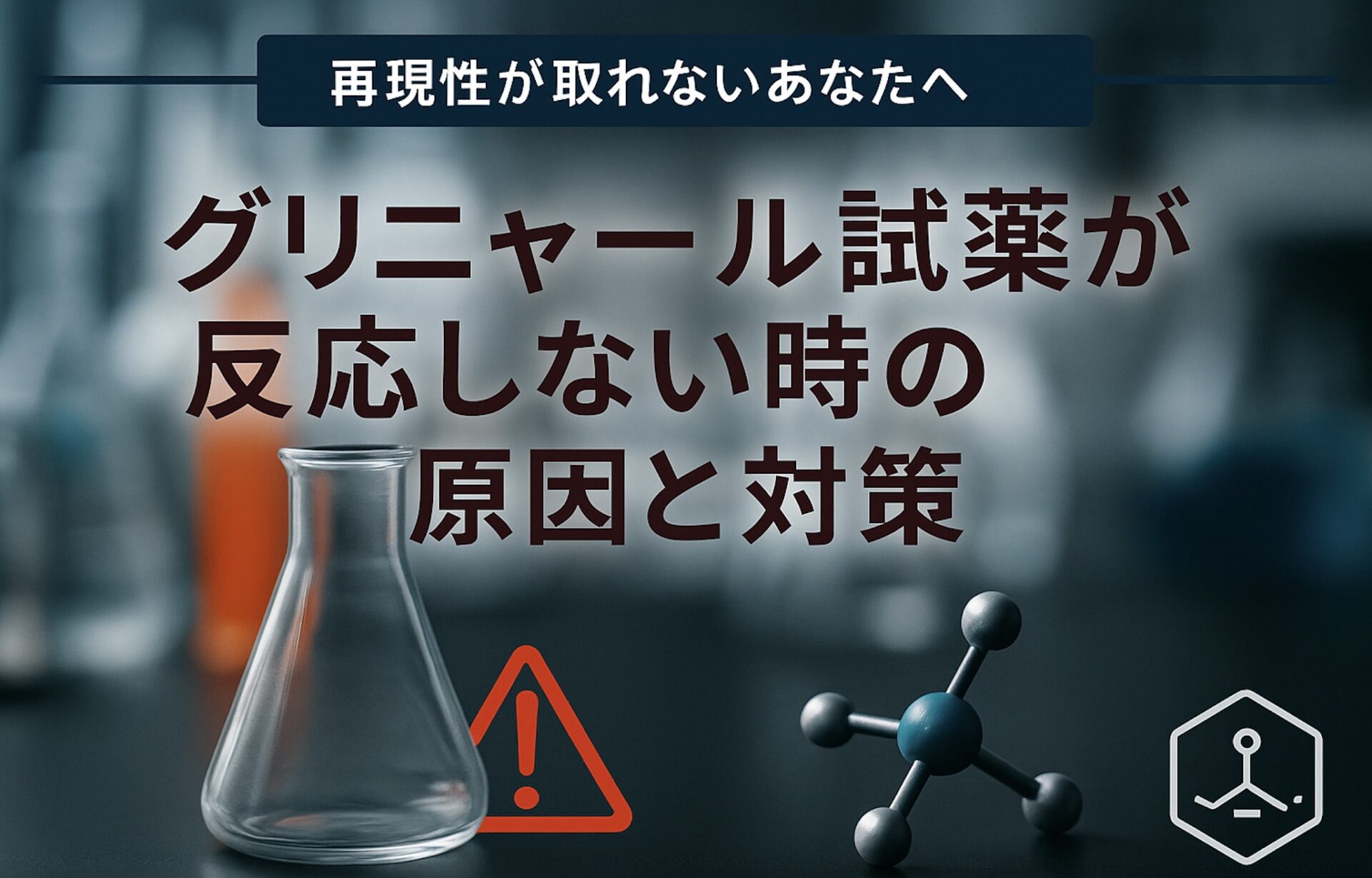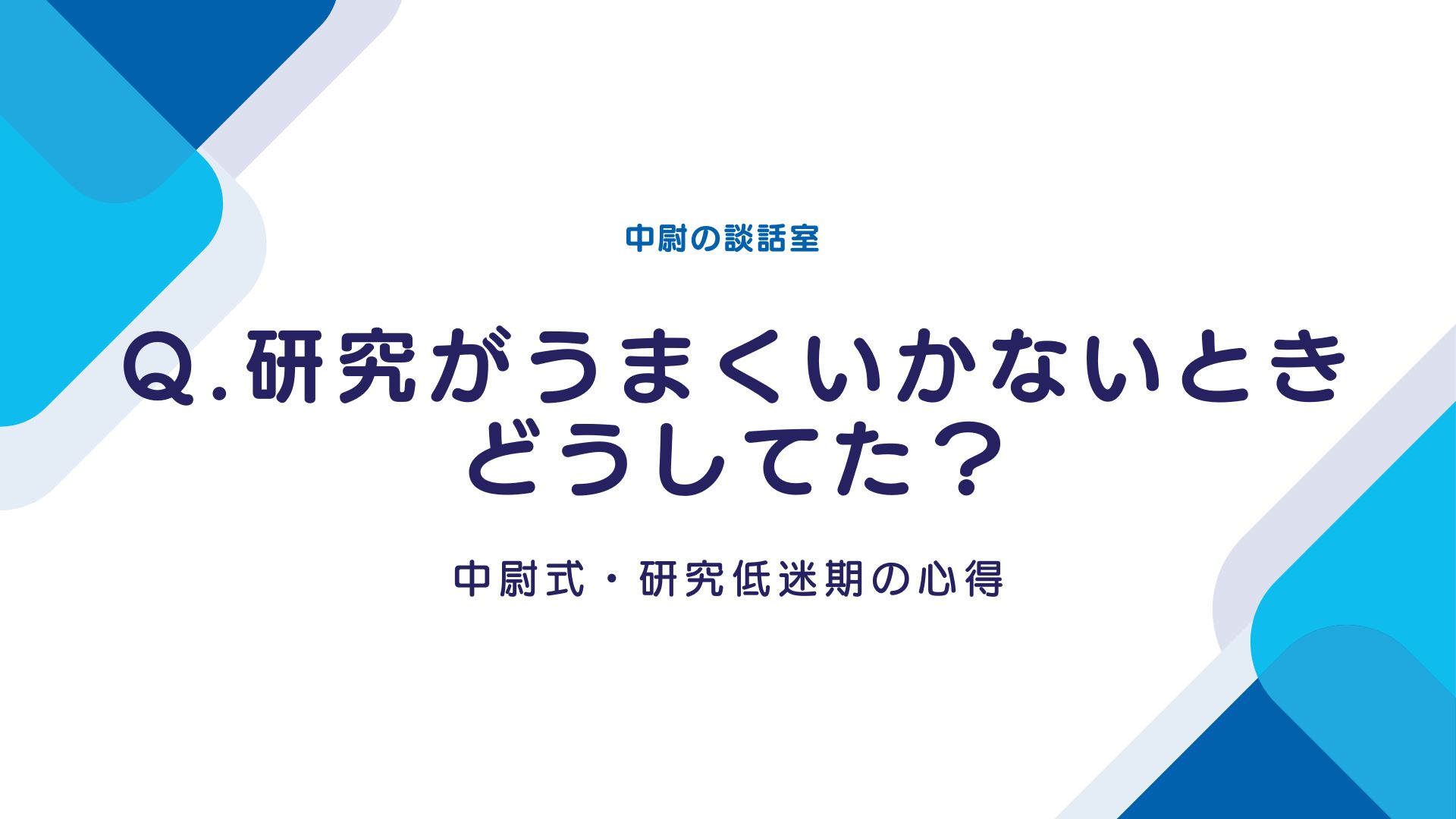カップリング反応がうまくいかない人へ 「Pd/Ni虎の巻」再現性編
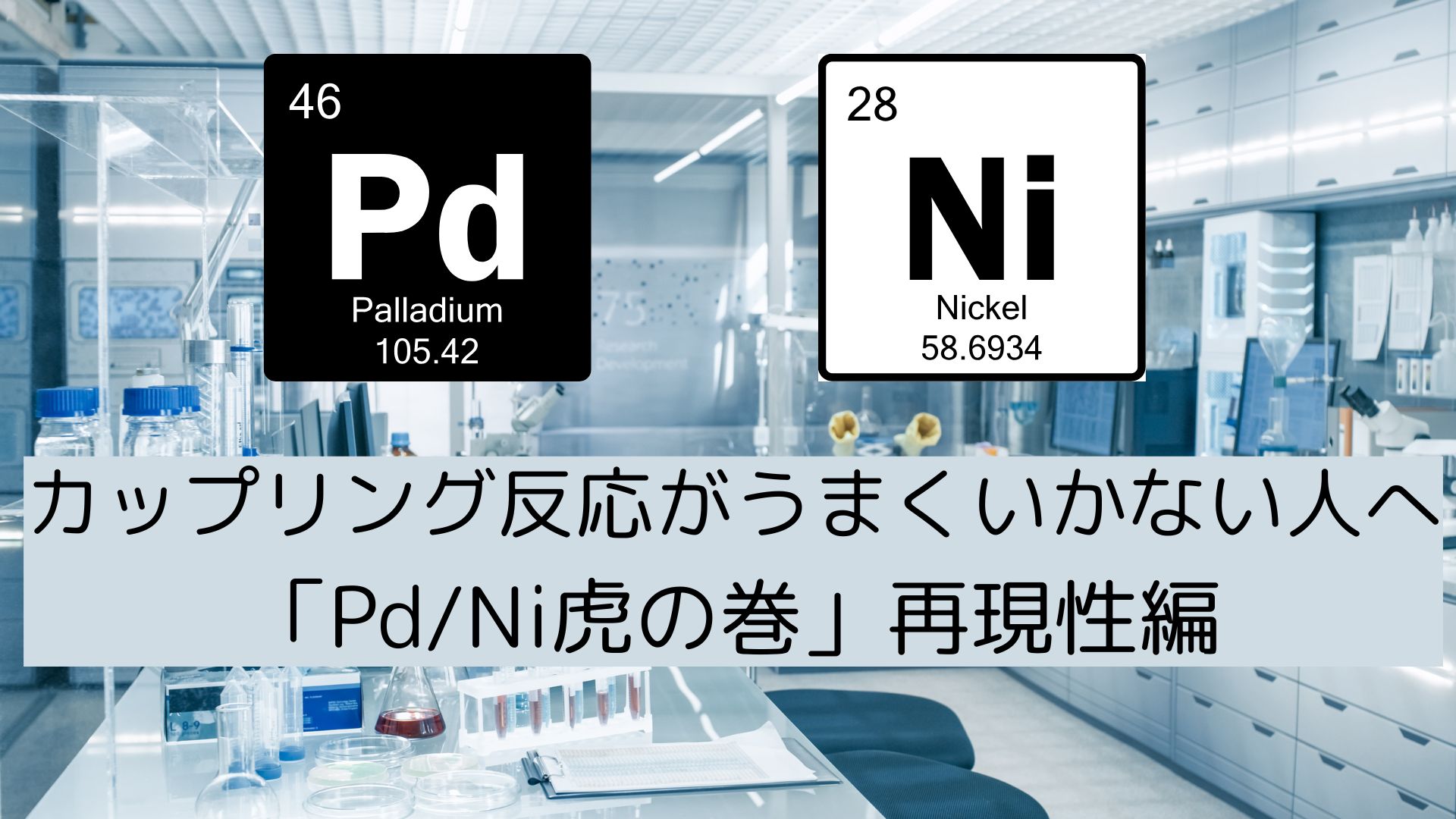
- 文献や先輩の実験の再現が取れない人
- 収率が安定しない、失敗の原因が分からず困っている人
- クロスカップリング反応初心者
今この瞬間も、世界のどこかでは“クロスカップリング”が行われている。
──それほど日常的になった有機合成には欠かせない存在。
材料開発や全合成、高分子化学者まで幅広い分野で活躍しているクロスカップリング反応
誰でも手軽に複雑な化合物を作れる画期的な手法として、ノーベル化学賞も受賞しています。
雑に混ぜるだけで進行する反応も多いですが、最先端の研究になればなるほど再現を取るのに一苦労することも。
「文献通りの収率が得られません。」研究室で一番耳にしたワードかもしれません。
今回は、パラジウム触媒とニッケル触媒を用いた反応開発のテーマで博士号を取得したミントガム中尉がちょっとした実験のコツを書いていこうと思います。
STEP1 邪魔者を排除せよ
遷移金属触媒(ニッケルやパラジウム)反応が進行しない理由の大半は不純物の混入にあると思っています。
特に混入しやすいのが水と空気(酸素)です。
以下に対策リストを書いてみたので参考にしてみてください。
夏場や梅雨の時期に再現が取れません。これは有機化学研究者のあるあるです。
高温多湿のこの環境、なんとか対策を立てていきましょう。
微量の水分で失活してしまう触媒たちを守ってあげられるのはあなただけです。
- 実験器具は徹底乾燥
反応に使うガラス器具に付着している微量水分を取り除きましょう。
オススメ方法は、反応直前に真空ラインで減圧しながらヒートガンで加熱すること。5分以上満遍なく加熱したらOKかも。
企業の研究室などヒートガンを使えない事情がある場合は、オイルバスで100度以上に加熱してみるという手もあります。
もちろん、洗浄後のガラス器具は加熱式乾燥機で半日以上乾かすことを忘れずに - 脱水溶媒を過信しないで
最近では脱水済みの有機溶媒が市販されています。非常に頼もしい存在ですが、過信は禁物です。
色々な人が同じボトルで実験する以上、丁寧な人もいれば雑な人もいます。(みんな違ってみんないい)
使用する過程で少しずつ、水が入ってしまうものなんです。
特にボトルの残量が少ない場合、すでに脱水溶媒ではなく吸水溶媒になっているかも。
教授にお願いして、新品のボトルに交換する。
500 mLボトルではなく、頻繁に交換できる100 mLボトルにサイズダウンするといったことを試してみてください。 - モレキュラーシーブ(吸着剤)を添加しよう
これだけ対策をしてもなぜか入り込んでくる水分
添加剤で強引に取り除いてしまいましょう。
ただし、モレキュラーシーブは酸や塩基など、予期せぬ働きをしてしまうこともあるのでお忘れ無きよう。
事前の活性化もお忘れなく。(真空引きしながらヒートガンで15分以上加熱)
我々が生きていく上では必要不可欠な空気もパラジウムやニッケルには毒となってしまうもの
彼らのために徹底的に酸素を排除していきましょう
- グローブボックスを使おう
グローブボックスで反応の準備を行えば酸素の混入は限りなくゼロにすることができます。設備が整っている人はスグに使いましょう。
そんな高級品持ってないよという人もご安心を、僕もグローブボックスがない環境で実験をしていました。
そんな人でもできる対策を書いていきます。 - 脱気・脱気・脱気
真空ラインでシュレンクテクニックなどを駆使して反応をしこんでいても、いつ酸素が入り込むかは分かりません。
窒素ガスをフローし続けたら防げるけど、強すぎると固体試薬が吹き飛んじゃいますよね。
固体試薬を全て投入したら真空引き→窒素置換を三回繰り返してください。
その後、液体試薬と溶媒を入れ終わったら再度脱気操作をしてください。
簡単な方法は、真空ラインで溶媒が泡立つまで真空引き、ブクブクしたらスグに窒素ガス封入を数回繰り返す、です。
(溶媒や試薬の沸点が低い場合は別報を、突沸や等量関係がメチャクチャになる危険性があります。)
凍結脱気やバブリング、真空引き法など脱気操作については別記事で詳しく解説するので参考にしてください。 - 実験器具を更新しちゃえ
グリースを最後に塗り直したのはいつだろう
そのセプタムは何実験そのままかな、穴やひび割れは無いだろうか
ちょっとした隙間や劣化からも空気は入ってきます。
消耗品は使い捨て、毎回交換して完璧な状態で実験しましょう。安全のためにも
STEP2 実験潔癖症になろう
試薬のボトルが変わったら反応が進みません、実験器具を変えたら収率が増えました。
そんな人は微量の「ゴミ」が原因かもしれません。
自分の部屋や実験机は汚くても、反応容器に関しては潔癖症になりましょう。
NMRではキレイでも検出できない不純物が反応を邪魔するのはよくあることです。
最先端の機械よりも自分の感覚を信じるべき時もあるのです。
- 試薬の見た目に変化はないかな
前まで透明だった試薬がうっすら茶色い気がする(トリエチルアミンなど)
この前は結晶だったのに、今回はフワフワしているな。
こんな違和感は決して見逃さないようにしましょう。
教授やPCではわからない、実験者だけが気づくことができる重要なヒントです。 - TLCを打ってみよう
TLCは身近すぎてみくびってしまいがちですが、高感度の分析手法です。
少量分析してみましょう。いつの間にやらスポットが増えてしまっているかも。 - 市販品を疑いましょう
市販の試薬をそのまま使えばOKなんてこともありません。
特に海外製の試薬は少し汚いこともあるんです。
TLCやNMRを駆使して純度を確認してから使いましょう。 - 精製法をマスター
上のような違和感がある場合は、ひたすら精製していきましょう。
NMRがキレイでも油断しないで、蒸留やショートシリカゲルカラム、再結晶など
あらゆる手法を駆使して純度を完璧に高めましょう。
別記事でもテクニックをまとめていきたいと思います。
どうしても取れないからと諦めていた黒ずみ、うっすらと付いている水垢
そいつらが再現性低下の犯人かもしれません。
徹底的に洗浄して器具も気持ちもキレイな状態で実験しましょう。
- 金属反応にはご用心
反応開発の条件検討では日常的にいろんな金属を使いますよね。
彼らは有機溶媒にも水にも溶けないことが多いです。
発煙硝酸など強酸を使用して完全に溶解させましょう。 - その器具は中和されていますか
酸や塩基を使用した後の実験には要注意
見た目はキレイでもガラス表面は中性じゃないかもしれません。
重曹水や塩化アンモニウム水溶液で中和を忘れずに。
発煙硝酸使用後もしっかり中和してくださいね。 - 純水置換を怠るべからず
洗い場で洗浄した後にはキチンと純水(蒸留水)で置換しましょう。
乾燥させたら無機塩まみれなんてこともあるかも
STEP3 論文や実験ノートと間違い探しを
論文(サポーティングインフォメーション)や実験ノートをジッと眺めると実は条件が違いました
なんてこともよくあります。僕もしょっちゅうやらかしてしまいます。
下のリストに間違い探しのヒント集を集めたので参考にしてみてください。
- 実験者の地域は?季節は?
文献の実験が夏のロサンゼルスだとしたら、同じ室温条件でも冬の日本では再現が取れないかも - 試薬は合っている?
例えば酢酸ニッケルは無水物と水和物で全然違う活性を持っています。
トルエンとエチルベンゼンで全く違う結果が出ることも。
ほぼ同じが通用しないのが世知辛いですが、完璧に揃えましょう - スケールは同じかな?
論文が0.1 mmolスケールの実験を10 mmolでやろうとしても上手くいかないかも。
その逆もまた然り、一度文献と全く同じ条件で試してみよう。 - 実験器具の種類はどうだろう?
シリカゲルと思い込んでいたらアルミナカラムということも。
攪拌子の材質の違いかも。
サポーティングインフォメーションのgeneralには使っている器具の詳細も書いてあります。
最後の奥の手:邪魔者投入、敵の敵は味方作戦
ここまで完璧にしても再現が取れない場合
一度発想を逆転させましょう。
紛れ込んでいた不純物が反応進行のカギだった。
こんなこともよくあります。原料の中にある「原料の原料」が触媒になっていたり、微量の水や酸素が効いていたり。
あえて邪魔者を添加してみる「敵の敵は味方作戦」に出てみてもいいかもしれません。
もし今まさに再現が取れずに悩んでいるなら、あえて水や酸を“ほんの少し”入れてみるという実験を一つ組んでみてください。思わぬ光が差し込むかもしれません。
おわりに
再現性を確かめている時間は、無駄な時間に思うかもしれません。
しかし、反応と向き合って、反応を深くすることにもつながる良い機会でもあります。
面倒臭いかもしれませんが、試薬の外観や実験条件など得られた情報は全て実験ノートに記入するように心がけましょう。(僕はよくサボって怒られていました)
あなたの反応の再現が1日でも早く取れることを陰ながら願っております。
Let’s Enjoy Organic Chemistry!