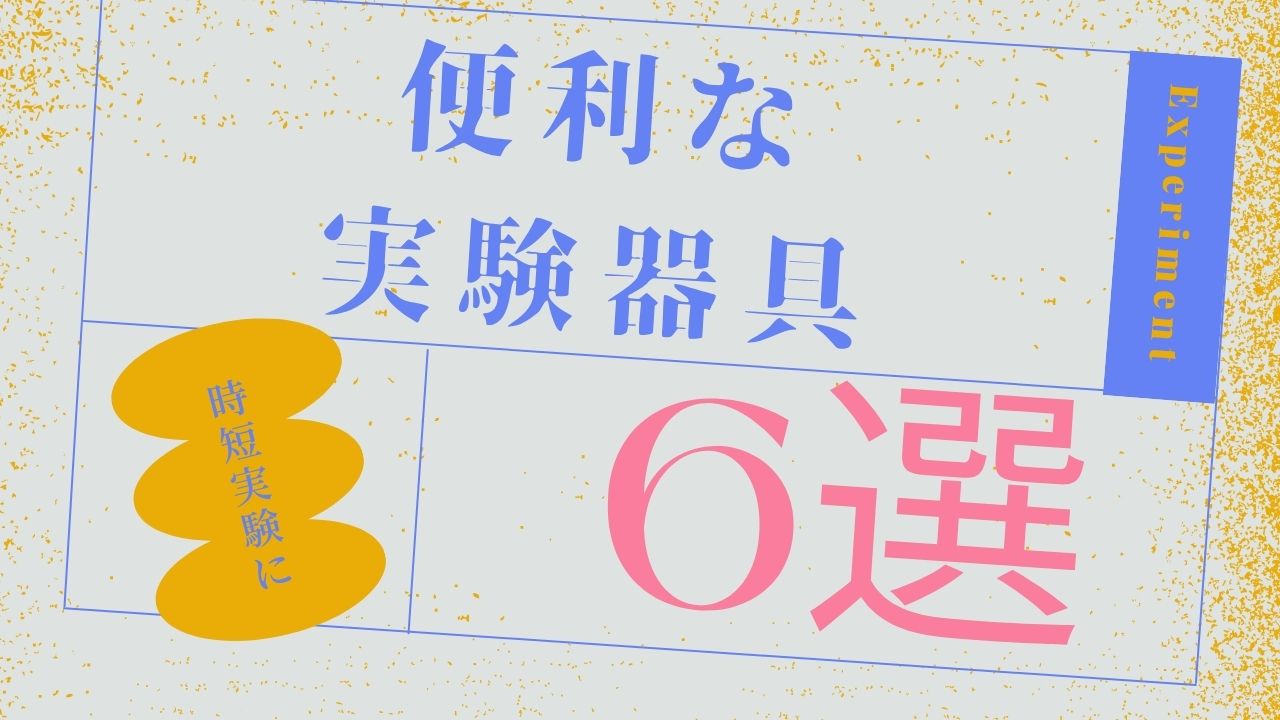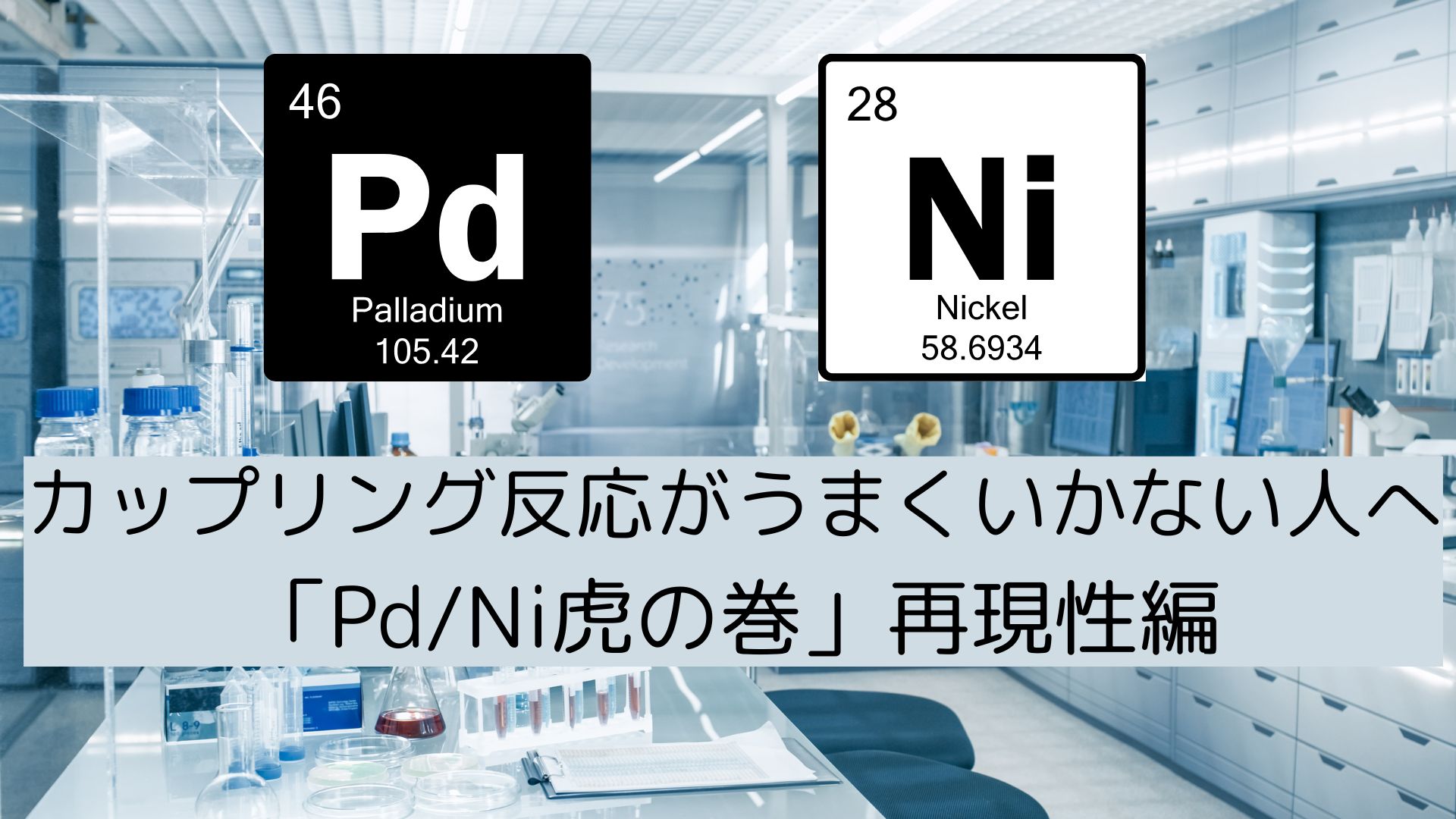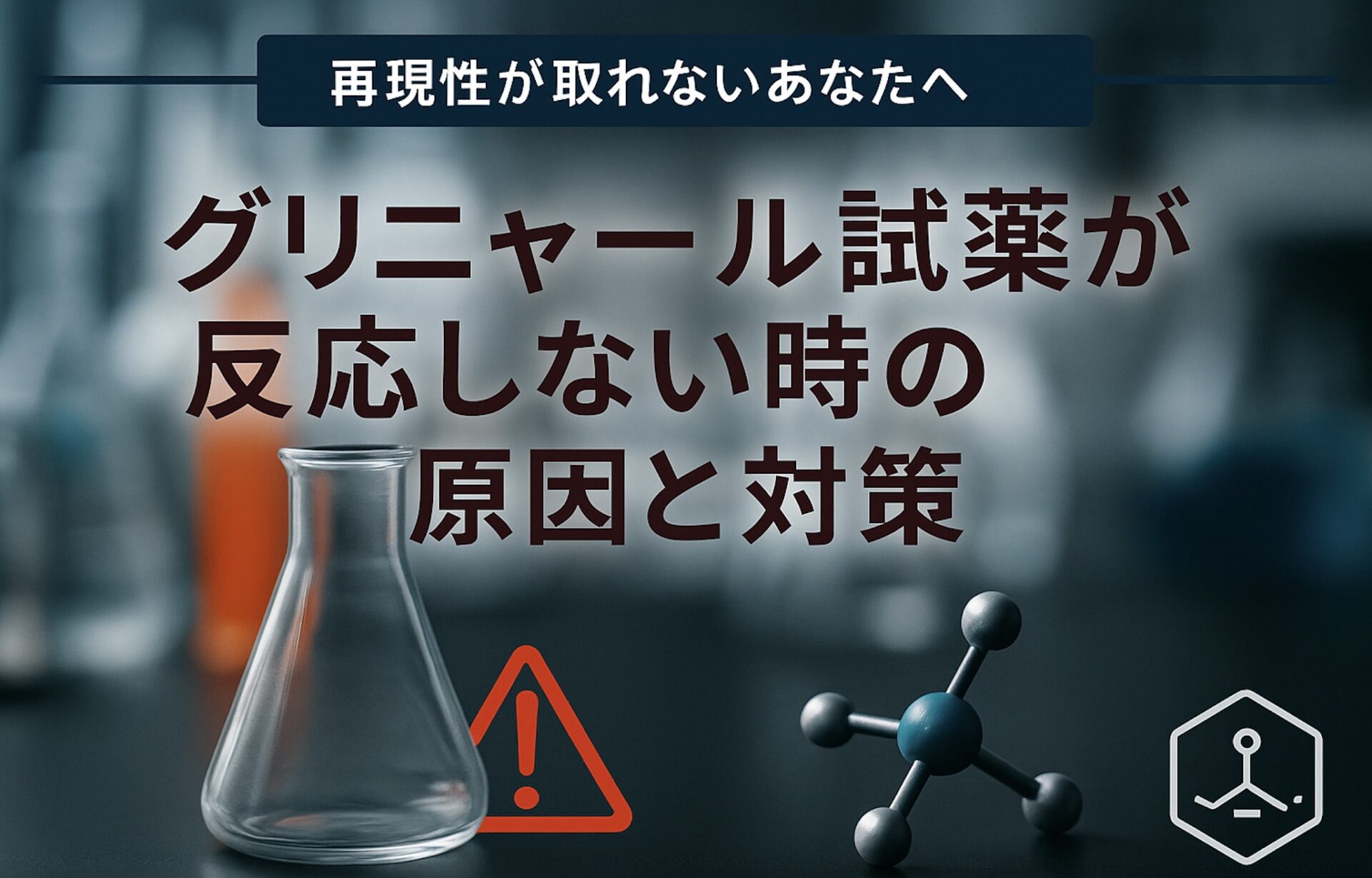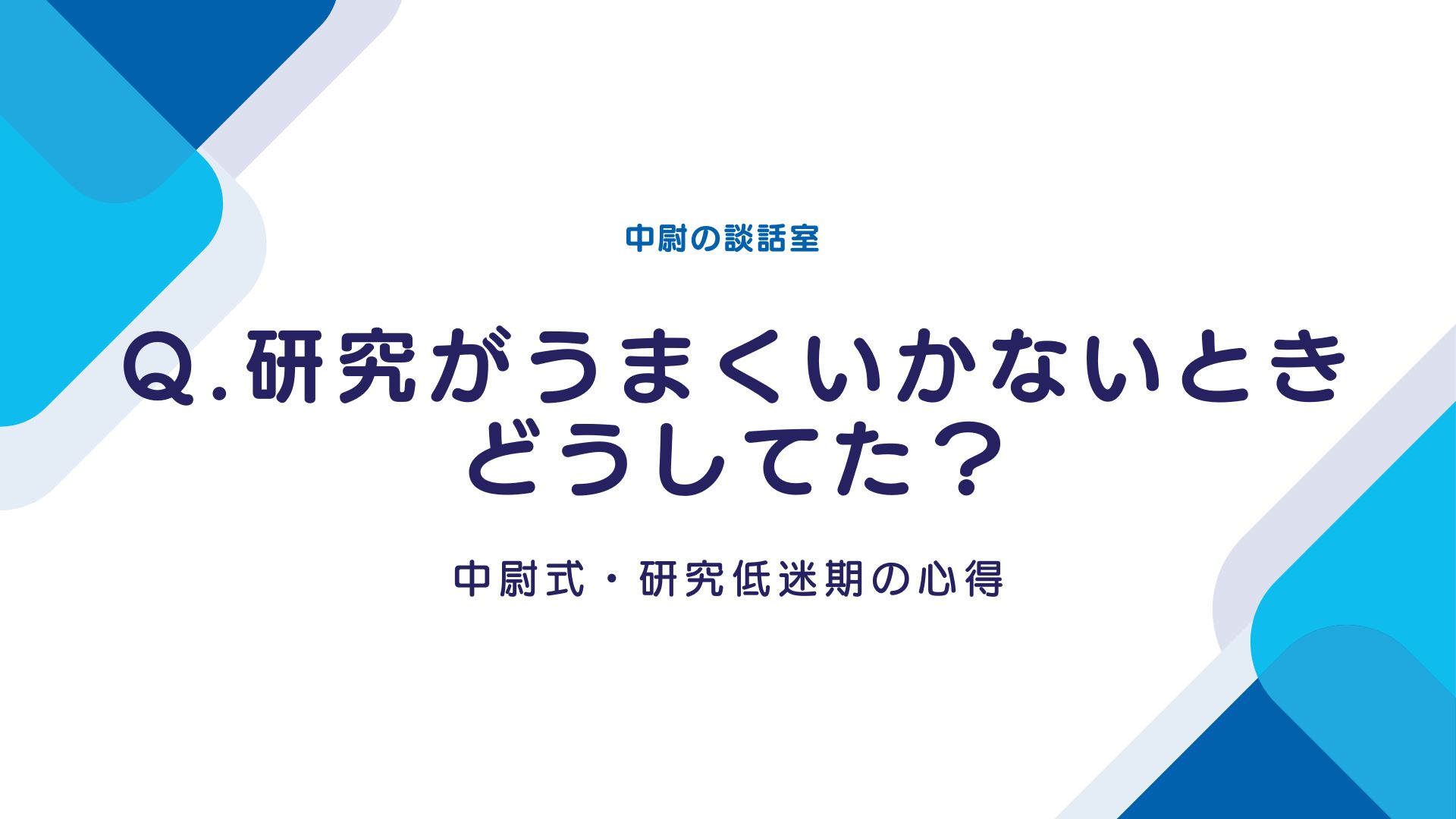ミントガム中尉流 研究テーマの決め方・見つけ方 「有機化学の新反応の作り方」
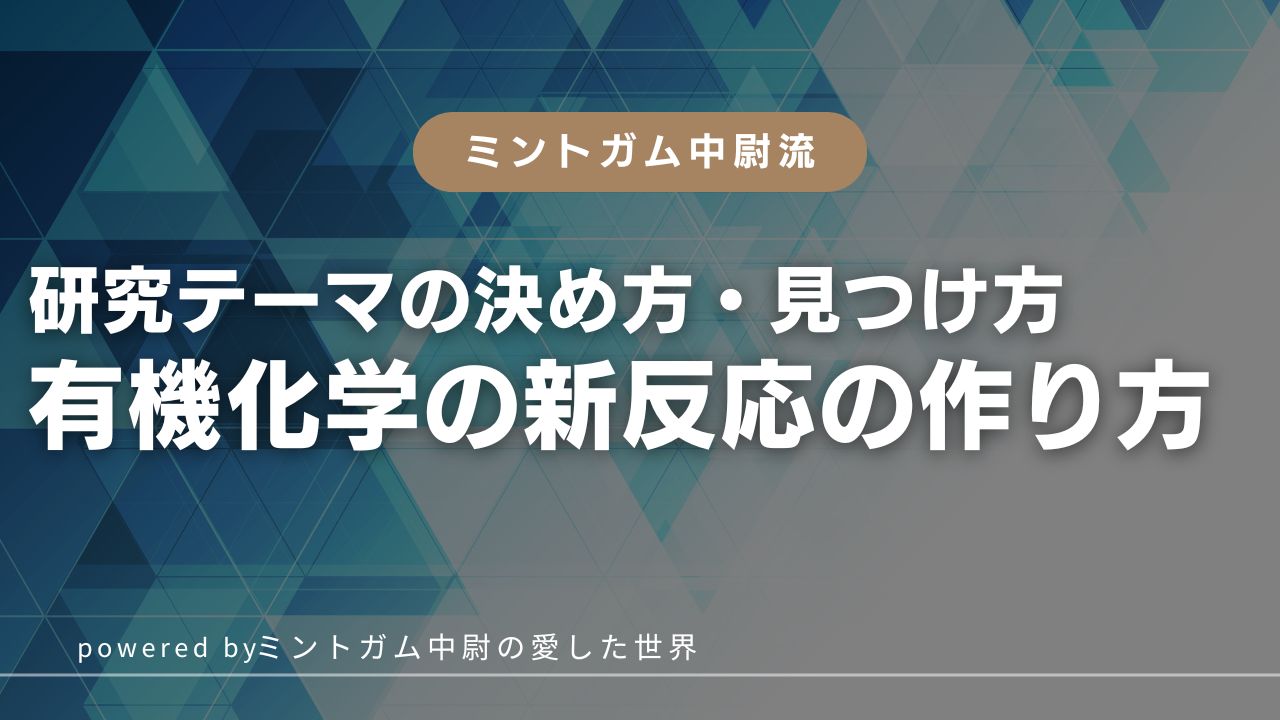
- 学部生や修士課程など
- 研究テーマに困っている人
- 新テーマを提案したいけど思い浮かばない人
研究室に慣れてきたタイミングで一度は思うこと
「教授や先輩にもらったテーマじゃなくて自分だけの研究をやってみたい」
かと言って、最新の研究に詳しいわけでもないし、面白い論文とつまらない論文の違いもよく分かっていない。
新テーマはどんな反応を提案すればいいのかと悩む日々
そんな悩めるあなたに、ミントガム中尉流の新テーマ提案術を伝授します。
ホームランにこだわらない
新テーマを考える時、どうしても意識してしまうのが「Nature、Science(世界トップレベルの論文誌)」
正直いって、いきなりそのような“ホームラン”を狙うのはかなり難しいです。
千里の道も一歩から、まずは“ヒット”で良いのでテーマを考えて発表するところまでを体験しましょう。体験に勝る勉強はありません。
かの範馬勇次郎も、刃牙が空想の巨大カマキリを倒したと聞いた際、こう言っていました「百聞は一見にしかず、百見は一触にしかず。(中略)想像はあくまで想像、実物の仔犬にも劣るシロモノよ」と(範馬刃牙3巻より)
僕も学部やM1の頃は“ヒット”論文を乱発していました。
胸を張って“ホームラン”と呼べる研究ができるようになったのはM2からドクターだと思います。
間違いなくこのホームランは何報ものヒット研究で、能力やセンス(感覚)を磨かなければ達成することはできなかったと思います。
新テーマの作り方3選
初学者でも簡単にできるテーマ開発方法は大きく3つあると思います。
キーワードは「副反応」「ミックス」「バージョンアップ」です。
それぞれ、詳しく説明していきましょう。
反応開発を行っている時って同じ反応を何百回もやらなくてはいけないので、流れ作業になりがちですよね。
流れ作業で反応を仕込んで、GCやNMRでターゲット化合物の収率を記録したらゴミ箱にポイしていませんか?
油断は禁物です。気を抜いていたらお宝を見逃してしまいます。
最低でも、マスバランス*が合っているかだけは確認するようにしましょう。
(マスバランスとは、原料の減り具合と生成物の量の関係のこと。原料が90%消費されているのに生成物が40%しかいない場合、50%分何かが起こっている)
マスバランスが合わない場合はチャートをよく見直したり、カラムをかけてみたりして奇妙な副生成物がいないか確認してください。
副生成物を目的物にするような研究は、もう立派な新テーマです。
しかも嬉しいことに、副生成物を合成する反応は絶対に進行します。しかも、今と「似たような条件で」です。
副生成物を発見したら、新反応開発は5割終わったと言っても過言ではありません。
副生成物が出るか出ないか運次第なところもありますが、普段の研究を進めながらも新反応を狙える画期的な戦法だと思います。
この項目は、かっこいい言い方をすると「オズボーンのチェックリストにおける結合」です。
(オズボーンのチェックリストはアイディア発想に役立つので調べてみてください。)
つまり、「自分の反応」と「お気に入りの研究」を組み合わせることです。
例えば、特殊な原料(求電子剤)で鈴木宮浦カップリング反応を開発している人がいたとしましょう。
そこに、バックワルトハートウィッグカップリング反応を組み合わせて、
求核剤をボロン酸からアミンに変えるだけで新テーマの出来上がりです。
このミックスレベルだと、簡単に思いつけるため同じ発想のライバルが多いことが玉にきずです。圧倒的な実験量でライバルより先に論文化してしまいましょう。
慣れてきたら、組み合わせる概念を「大きく」「遠く」していけば研究のレベルはどんどん上がっていきます。
例えば「酸化還元反応」と「光」を組み合わせたら一大ブームを巻き起こした「フォトレドックス反応」が出来上がります。
「有機合成」と「磁力」とか面白いかもしれませんね。
あなたの反応の欠点を、宇宙で一番分かっているのはあなたです。
その欠点を解決してパーフェクト反応を目指すと言うのも新テーマとして立派なものです。
例えば150℃かかる反応を60℃にしたり、高価なパラジウムをニッケルにしたり、使えない基質を適用できるようにしたり
論文として発表した反応も改善できるところは無数にあるんです。
ここを解決したような例で言えば、毒性の高いクロム酸化を触媒量に減らした研究とかがあります。
この改善により一気にユーザーは増えたんではないでしょうか。
新規性は弱いかもしれないですが、「使われる反応」にする「反応のツール化」も有機化学者の重要な使命です。
最終関門:ボスの説得〜闇実験のススメ〜
研究テーマを考えた後、実際に取り組む前に立ちはだかるのが「ボスの壁」です。
どんなに独創的で素晴らしいアイディアを思いついてもボスのGOがなければ日の目を見ることがなくなってしまうのが若手研究者の辛いところです。
僕の元ボスは新テーマ提案大歓迎だったのですが、新テーマをなかなか認めない、許してくれないボスもいるとよく聞きます。
そんな時にオススメなのが「闇実験」です。
アイディアだけ説明してもなかなか納得してもらえない時は、少しだけ実験成果も合わせて持っていくと一気に説得力がUPします。
この反応は実際に行くんだ、この条件で取れるならこんな改善の余地があるな、、、とボスに考えさせることができたらテーマとして認めてもらえる可能性も高くなるでしょう。
この少しだけ結果を添えると言うやり方は、大学教授が科研費などの研究費を獲得するための申請書の説得力を増すために使うテクニックでもあります。
そんな闇実験を始めるために守っておきたいルールを教えておきます。
- 危険なことはしない
当たり前ですが、テーマ外の実験で事故を起こすことは絶対にやってはいけません。
安全である保証ができる実験のみ行うことが鉄則です。 - 新しく試薬を買わない
初めのうちは、ラボに転がっている試薬で試行錯誤しましょう。研究費を使用して高価な試薬を試すのは、認められてからにしましょう。
知り合いの先生はこれを「チャーハン実験」と呼んでいました。 - 本業のテーマをおろそかにしない
本テーマと新テーマ探索の割合は7:3ぐらい(多くても6:4)にとどめておきましょう。
自分が考えたテーマの方が力が入る気持ちはよくわかります。
しかし、求められている結果をきちんと出した上で、自由な発想でチャレンジするのが一人前の研究者です。 - 怒られたら止める
闇実験もバレることはあります。
もしも怒られてしまった場合はタイミングが悪かったと諦めて、素直に寝かせておきましょう。
ほとぼりが冷めた頃合いに再チャレンジしてください。
バレたら全力でアピールして認めてもらうという手もあります。
おわりに
僕の学生時代の恩師が「学生の仕事は、教授の手のひらの上を全力で走り回ることだ」と言っていました。
教授の手のひら(研究室の研究テーマ)を芯に置きつつ、新しい発想で全力で走り回る(研究をする)。
そうすると、いつの間にか研究者としての知識やスキルが身についているものです。
皆さんも教授の手のひらの上を全力で駆け抜けながら、指先の一歩奥を目指して新テーマの開発にチャレンジしてみてください。
自分でテーマを考えられるようになったら、研究の楽しさは100倍にも1000倍にも膨れ上がりますよ。
あなたの考えたテーマを論文として読める日が来ることを楽しみにしています。
Let’s Enjoy Organic Chemistry!